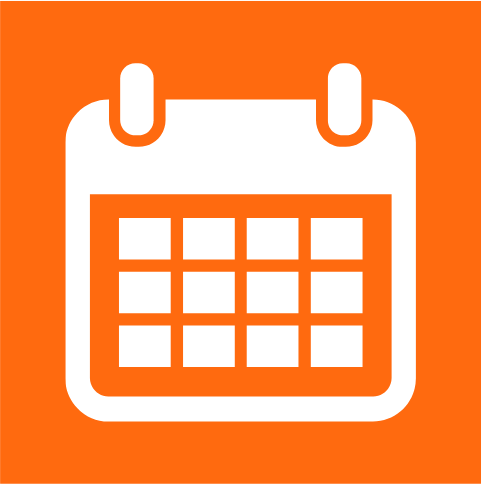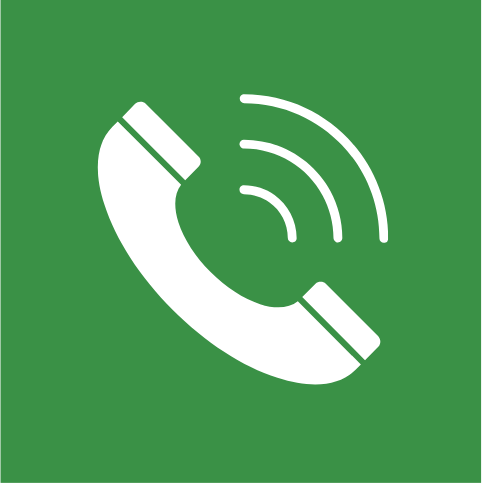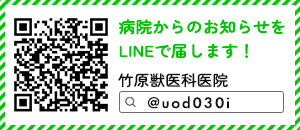犬にも血尿や頻尿がある?膀胱炎の原因・症状から治療・予防法まで解説します2025.05.13

人間でもおなじみの“膀胱炎”ですが、犬も比較的多くかかる病気です。
「生死にかかわる病気ではなさそう」というイメージもあり、飼い主様のなかには愛犬の尿に異変があっても様子見される方もいるようです。
ただ、膀胱炎の原因は多岐にわたり、初期症状を見逃して進行すると症状が悪化しやすい病気です。ほかの病気の合併症で起こっていることもあります。
早く気づき早期治療を進めることができれば、犬の辛さを緩和してあげられます。
今回は、犬の膀胱炎の症状や主な原因、飼い主様だからこそできる予防法について分かりやすくお伝えしていきます。
目次
犬の膀胱炎って?主な特徴をわかりやすく解説
まず、犬の膀胱炎の仕組みや特徴について見ていきましょう。
膀胱炎の仕組み
犬は、
・尿を作り出す器官「腎臓」
・その尿を膀胱へと運ぶ「尿管」
・尿管から運んだ尿を溜める「膀胱」
・外に排出する通路「尿道」
という流れで排尿しています。
このうち尿を溜める膀胱で炎症を起こすのが「膀胱炎」です。
犬の尿道口はふだんから外部に触れるため、細菌や汚れなどが侵入しやすい状態となっています。それが「犬は膀胱炎を発症しやすい」と言われる背景です。
膀胱炎になった犬が見せる主な症状
膀胱炎になると、
・排尿回数が増える(1回の量がかなり少ない)
・尿に血が混じる(赤や茶色など)
・排尿時に痛がる
・排尿したいのに尿が出ない(排尿困難)
・お漏らし(トイレ以外で排尿する)
などさまざまな症状を見せます。
炎症によりいつも通りに尿が出なくなります。1回の排尿時の量が少ないことから、何度も尿をする“頻尿”も膀胱炎でよくある症状です。
おしっこするたびに痛みで鳴くことや、排尿のポーズをしても排尿できない“排尿困難”になることもあります。
残尿感も膀胱炎の症状のひとつです。犬の場合、言葉が話せないので残尿感については分かりづらいかもしれません。尿を出し切っているのに排尿のポーズをずっとしているなら、残尿感を感じている可能性があります。
“尿”以外の症状はあまりないこともある
膀胱炎が初期の頃は、“尿”に関連すること以外は特に異変が見られないことも多いです。食欲もあって元気なので、飼い主様としては「様子見でもいいのでは?」と思いがちかもしれません。
ただ、膀胱炎が悪化したり、膀胱炎の背景にある大きな病気を見逃してしまうと、いずれ重度な症状が全身へ現れてくることもあります
初期に気づけず重度の膀胱炎になると、腹痛や嘔吐、発熱、食欲不振をともなう合併症にもつながることもあるため、早期発見で治療をすることが重要です。
なぜ膀胱炎になるの?犬の膀胱炎の主な原因を知ろう

膀胱炎の主な原因を見ていきましょう。
原因①:細菌感染
一番多い理由が細菌によるものと言われています。尿道から細菌が入りこみ、膀胱に到達して炎症を起こします。
通常、細菌が尿道口から膀胱へと侵入しても「何度も排尿する」ことで細菌は尿と一緒に外に出ます。尿が普通に出る場合は、膀胱炎の症状悪化の心配もありません。
ただ、
・免疫が低下して尿が出づらい
・ふだん水をあまり飲まずに尿を作りづらい
・排尿を我慢する
・下痢などで陰部が汚れた
などの犬は、細菌が尿と一緒に出る前に増殖し症状が悪化するでしょう。
尿が出ないことは、「細菌が膀胱に長くとどまる状態」なのです。
また、細菌感染による膀胱炎は、メスの犬に多い傾向です。オスよりも尿道が短めであり、尿道口から入った細菌が膀胱へ到達するのが早いことなどが原因と考えられています。
原因②:膀胱結石(尿石症)
次に多いのが膀胱結石(尿石症)による膀胱炎です。
膀胱結石とは、尿をためておく膀胱の中にできた“石”です。
膀胱結石が膀胱内にあるうちは、膀胱粘膜を傷つけたり、細菌の温床となったりして、膀胱炎の原因となります。しかしその石が突然移動して尿道に詰まると、犬は尿を出すことが出来なくなり、急性腎不全に陥ります。尿が完全に出なくなると腎臓に強い負担がかかり、犬は食欲低下、嘔吐、元気消失などの症状を示し、命にかかわる可能性があります。また、尿を全く出せないという症状は、犬にとってとてもつらいものとなるでしょう。
犬の結石の成分として代表的なものは「ストルバイト」と「シュウ酸カルシウム」です。これらは、尿の細菌感染や、食事中に含まれるミネラル分、膀胱内のpH値、尿の濃度、遺伝子などさまざまな要因が絡んでいると考えられています。
原因③:病気やストレスによるもの
他の病気により膀胱炎を起こすものとしては、以下のものが良く見られます。
前立腺疾患:主に未去勢犬における前立腺肥大症や前立腺がん
膀胱にできた腫瘍やポリープ
糖尿病などの内分泌疾患
肝門脈シャントにおいて発生するアンモニア尿石によるもの(まれ)
また、ストレスで免疫が低下して細菌に感染しやすい体となって膀胱炎を起こすこともあります。
・毎日のように長時間留守番させている(孤独感が強まる)
・引っ越しで環境が変わった
・新しい犬を迎えて我慢を強いられている
・家族構成の変化で見知らぬ人と暮らすようになった
などは犬にストレスになりやすいことです。
少しでもストレスを少なくできるよう、環境や接し方の配慮をしましょう。
特に、免疫がふだんから低下しているシニアの犬は、細菌感染も起こしやすく、結石が膀胱へ大きな刺激となるケースもあります。ストレスで免疫低下を起こさないように、散歩や運動不足に注意しましょう。
動物病院での診断の流れと実施される主な検査方法

膀胱炎の原因はさまざまあるため、必要に応じていくつかの検査をしながら診断します。
問診
飼い主様から、どんな症状がいつ頃から出ているかをお聞きします。問診の際に、的確に伝えられるように時系列にメモにまとめておくといいでしょう。
触診
お腹を触って、犬が痛みを感じていないかのチェックを行います。触診によって膀胱の異常もある程度確認できます。
尿検査
膀胱炎の疑いが強いと判断されたら、尿検査が一番初めに行う、もっとも大切な検査です。まずは尿の採取する採尿が必要です。
ご自宅で自然に排尿した自然排尿の尿を検査に使うこともできます。しかし、汚れや細菌が混じると検査結果に影響することもあるため、病院で採尿したもので検査されることが多いかもしれません。ただ、いざ病院では尿が溜まっていなかったり、採尿できない状況だったりする可能性もありますので、飼い主様が尿を持ち込むこと自体は、有益なことでしょう。
※尿のとりかた
100円ショップなどで販売されているお弁当用の醤油さしなどが便利です。キャップを外してそのままスポイトのように採取することができます。
普段、排尿をシートにする子は、シートを裏返して吸収されなかった部分をスポイトなどで取りましょう。
外で排尿する子は、清潔な白色トレイなどで直接受けるか、アスファルトなど不純物が混じりにくい場所でした尿を、なるべく汚れを一緒に吸い込まないようにして採取してください。
採取後は冷暗所に保管し、すぐに病院へ持ちこみましょう。
尿院での採尿方法には、「カテーテル採尿法」「膀胱穿刺尿」という方法があります。
尿道にカテーテルを入れて直接尿を採ることができるカテーテル採尿法は、オスの場合は比較的やりやすい方法です。
メスの場合は、膀胱に直接針を刺す方法が行われます。針を刺すと聞くと、怖い印象を抱かれるかと思いますが、実際には尿道にカテーテルを入れるよりも短時間で済みますし、むしろカテーテルよりも嫌がらないことが多いです。穿刺による採尿は、より正確な検査結果が得られる方法でもあります。
レントゲン検査
レントゲン検査は、通常、骨の異変を見つけるのに優れた検査です。膀胱や尿道に石が発生していないかの確認はレントゲン検査で行います。特に石の数や形を確認したり、膀胱以外の石(腎臓、尿管、尿道)を評価したりするのに必要な検査です。
犬の膀胱結石の多くは、ストルバイトおよびシュウ酸結石であるため、それらはレントゲンでの評価が可能ですが、その他の石(シスチンやアンモニウムなど)はレントゲンに写らないため、レントゲン検査で異常がなくても、エコー検査を同時に行うケースもあります。
レントゲン造影検査
明らかな感染性膀胱炎や結石性膀胱炎をのぞく血尿や難治性膀胱炎には、逆行性膀胱造影検査(二重造影検査)を実施することもよくあります。特に膀胱腫瘍、前立腺腫瘍の診断に有効です。尿中B-LAF遺伝子検査と組み合わせて、早期の診断を目指しています。
エコー検査
エコー検査は、膀胱の状態を詳細に把握することのできる方法です。特に軽度の結石症や比較的早期の膀胱腫瘍も発見できる可能性があります。慢性膀胱炎では、腫れにより膀胱の粘膜に厚みをおびている場合もあります。またポリープ病変や膀胱腫瘍、前立腺の状態などの把握にもエコー検査が必要です。しかし、エコー検査単独による診断ではなく、他の検査も組み合わせた判断が必要です。
犬の膀胱炎はどう治す?主な治療方法と治療期間について
愛犬が膀胱炎と診断されると不安ですよね。主な治療方法や治療にどのくらいの期間を要するかを解説していきます。
治療方法
膀胱炎の原因によって治療方法は変わりますが、投薬や食事療法がメインとなります。
細菌による膀胱炎の場合、「どんな細菌か?」の特定をし、抗生物質・消炎剤などで治療を進めていきます。また排尿量を増やために点滴を行い、うすい尿をたくさん作ることで症状を軽減したり、治りを早めてあげることも期待できるでしょう。
尿路結石が起こっている場合、それがストルバイト結石であるとみられるときには、結石を溶かすために内服薬を用いたり、療養食を使うことがあります。ただ、結石が大き過ぎて投薬治療では結石を溶かせないとき、大きな結石が尿道を塞いで危険なときは、外科手術が必要です。結石がシュウ酸カルシウム結石と推定された場合も、外科手術が必須となります。
そのほか、腫瘍が原因となっている膀胱炎なら、根本的な治療として「腫瘍を摘出する」「抗がん剤を使用する」などといった治療が欠かせません。
治療期間
感染性の膀胱炎が疑われ、発見が早期であれば治療も行いやすく、治るまでの期間も短めです。炎症具合を経過観察しながら投薬治療を続けます。
早期に見つけた軽症の膀胱炎なら数日~1週間以内に症状がおさまることもあるでしょう。
ただ、場合によっては数週間と治療に長い期間を要することもあります。
勝手な判断で治療を中止しない
膀胱炎は、尿の異変があっても元気や食欲に変化がないことも多いです。
投薬は2~3週間も続けることもありますが、飼い主様が「もう治ったのではないか」と勝手に治療を中断すると、細菌が無くならずに再発をすることもあります。
細菌性の膀胱炎の場合は“治ったこと”の確認を獣医師により判断してもらうまでは油断できません。
何度も再発させないように、動物病院にて診察・治療を進めていくことが大事です。
膀胱炎の予防法と日常のケア

飼い主様が意識することで膀胱炎の予防につながることはたくさんあります。日常的に行えるケアについて見ていきましょう。
トイレを我慢させない環境
排尿したいのにできない状況が長引くことで、膀胱に尿が留まる時間が増えて炎症を起こすことがあります。
よく「散歩のときしか排泄させていない」という飼い主様もいらっしゃいます。ただ、雨風など天気の状況や飼い主様の散歩に連れていく時間帯の変化などにより、愛犬のトイレタイミングを我慢させることにもなりかねません。
散歩の際に排尿・排便することに加え、お部屋のなかでもトイレを設けて好きなタイミングで排尿できる環境を整えておくのも膀胱炎の予防につながります。
清潔を保った環境に
細菌が尿道に入り込むと感染することもあります。
不衛生な環境での暮らしは、膀胱炎にもつながるので注意しましょう。
人間と違って犬の尿道の入り口は露出しています。陰部がお尻と近いメスの犬の場合、便から細菌感染を起こすこともあります。
細菌が感染しづらいように、ふだんからお尻周りの清潔を保つことが大切です。
水分をしっかり摂らせる
飲み水が足りないことが膀胱炎を引き起こすケースもあります。
特に、寒い冬になると「あまり水を飲まない」という犬も多いです。飼い主様が積極的に水分を飲ませてあげることで予防につながります。
尿の量、回数などを観察する
膀胱炎になると、
・尿の色が変化する(濃い色)
・アンモニア臭が強くなる
・尿の回数が増える
・排尿時に痛がる
など“排尿”に変化が起こるものです。
少しでも愛犬の尿に変化があった際には、膀胱炎の可能性があります。獣医師に相談することが大事です。
まとめ
犬の膀胱炎は、それほど珍しくない病気です。細菌や免疫低下などで発症することがあります。ただ、尿以外については異変がなく、「いつもと変わらず元気」ということも少なくありません。
そのため、初期症状を見逃しやすい病気です。膀胱炎は自然に治るものではありません。治療せず放置すると、膀胱以外に影響が広がり重度な病気を引き起こすこともあります。
少しでも早く見つけて治療を進め、犬への負担をおさえてあげましょう。
また、異常を感じた際に受診することももちろん大切ですが、健康診断を定期的に行うことで体全体のケアにもつながります。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |