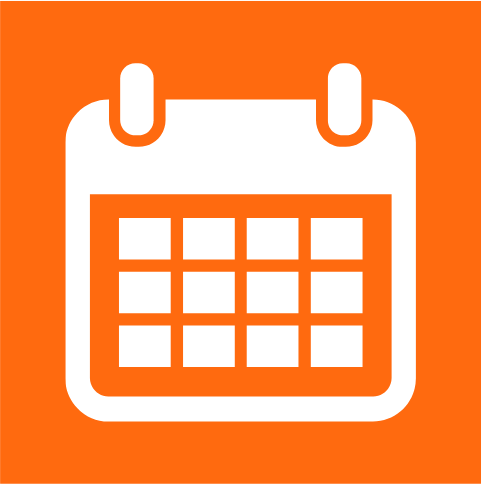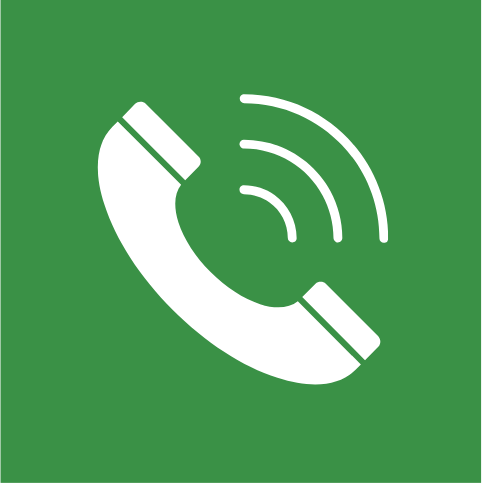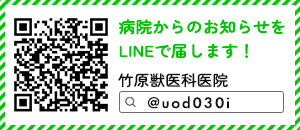【注意!】マダニによる人・犬・猫の感染症が発生しています。外に行く全ての犬猫に、ノミ・マダニ予防を実施してください。2025.07.31

暖かい気候とともに活発になるノミ・マダニ。
とても小さく肉眼では見づらい生物ですが、実は身の回りにはたくさん存在しています。
当院ではこれまでもノミ・マダニ予防に力を入れてきましたが、今年は特に、マダニが媒介する病気によるヒトの死亡例も多く耳にします。ヒトの命を脅かすマダニ媒介性感染症は、犬猫にも重大な病気として知られています。
今回の記事では、犬や猫に寄生するノミ・ダニの特徴や予防策などを解説しますが、特に最近ニュースでも話題となっている比較的新しい感染症であるSFTSについて、当院から飼い主の皆様に知っておいていただきたいことをお伝えします。
ノミやダニにとって全身を“毛”で覆われている犬や猫は絶好の住処。気づかないうちに、ダニ・ノミが愛犬や愛猫の体で増殖している可能性もあります。
ダニやノミに血を吸われると、皮膚や耳などの炎症やかゆみで犬や猫はとてもつらい症状を感じます。そればかりか、一緒に暮らしている人間にも影響があるのです。
目次
犬・猫に寄生するノミやダニ、その種類と生態を理解しよう
はじめに、ノミやダニについて、どんな生物なのかを具体的に見ていきましょう。
ノミ
日本でよくいるノミは「ネコノミ」で、1~3㎜くらいの茶色い虫、昆虫の仲間です。大きさ的に肉眼でも発見しやすいサイズですが、ジャンプして俊敏な動きをするので見失うことも多いです。
ノミは動物や人間の血を吸って繁殖する虫で、猫や犬の毛に潜んでいるケースもあります。動きが素早く、室内に入った後にはベッドなどの寝具で増殖することも多いです。
ダニ
ダニは蜘蛛の仲間で、ノミと比べると小さいです。特に、春から夏に向けて繁殖が活発となります。ダニのなかでも少し大きめの「マダニ」と、小さく肉眼で見えづらい「ヒゼンダニ」がいます。今回の記事では主にマダニを中心に解説しますが、他のダニも犬猫の健康上重要であり、混同されている方も見受けられますので、ここで簡単に触れておきます。
マダニ
「マダニ」は、ダニのなかでも大きい体長です。成虫に育つと5㎜前後ほどですから肉眼でも見えますが、犬や猫の毛のなかで隠れているため見つけづらいです。血を吸うと数倍以上に大きく膨らみ姿が目立ちます。
マダニに吸血され病原体が体内に入り、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)や日本紅斑熱、ライム病、猫ヘモプラズマ症といった病気に感染するケースがあります。
特にSFTSは、人と動物の共通感染症であり、致死率が高く注意が必要ですので、後半で詳しく解説します。
ヒゼンダニ
ヒゼンダニは0.2~0.4㎜と肉眼では見づらいほどの小ささです。
疥癬とよばれるセンコウヒゼンダニは、動物の皮脂をエサとし、皮膚にトンネルを掘るようにして寄生することで、犬猫に猛烈なかゆみを伴う皮膚病の原因となります。初期では毛があまり生えていないところにいるのが特徴的です。
また、犬や猫の耳に寄生するミミヒゼンダニもいます。0.3~0.4㎜で肉眼では見え耳の“外耳”と言われるところに寄生するのが特徴です。
寄生されると耳垢が黒く臭いもひどくなり、「頭を振る」「前脚で耳を掻こうとする」「耳を床にこすりつける」といった症状を見せます。特に仔犬、仔猫で発症が多く、迎えたての仔には耳垢検査をお勧めします。
ツメダニ
梅雨時期から秋頃まで活動が盛んなダニで、大きさは0.5~1㎜ほどです。家に生息するチリダニやコナダニなどをエサとして生息しています。チリダニはアレルギー症状を引き起こす原因となるだけで刺すことはありませんが、ツメダニは人を刺し痒みなどを引き起こすこともあります。
ハウスダストマイト
ヒトのアレルギーでは、ハウスダストが大きな原因とされています。室内の布製品や寝具、ホコリなどに存在するダニとその糞や死骸は、主なハウスダストの一つです。このダニはハウスダストマイトとよばれ、主にコナヒョウヒダニやヤケヒョウヒダニが知られており、肉眼では見えないサイズです。
これらは犬猫にもアレルギーを起こすことが知られており、特に犬アトピー性皮膚炎の発症に大きく関与しているといわれています。
ノミとマダニの見分け方
肉眼で見えるノミとマダニの見分け方を解説します。
ノミ
・2-3㎜の縦長の体。茶~黒色
・動きが素早く、毛をかき分けると奥の方に素早く移動したり、飛び跳ねたりする。
・細かい黒いカスのようなノミ糞が、動物の体や床敷きについていることが多い。
・尾の付け根や腰背部、内股などに寄生することが多く、動物は痒がる。
マダニ
・3-5㎜程度の平たい体。吸血すると1-2㎝程まで大きくなる。
・吸血前は暗赤、茶、黒色など。吸血で大きくなったものは黒、灰、黄土色など様々。
・動きはゆっくりで、毛の上を歩いていたり、既に皮膚に食いていることも多い。
・体のどこにでもつく可能性があるが顔周囲は多い。動物は痒がらない。
番外編:その他の眼に見える外部寄生虫 シラミとハジラミ
シラミ…薄褐色~褐色。毛をかき分けた皮膚に付着していることが多く、吸血する。
ハジラミ…薄褐色~褐色。毛に付着していることが多く、吸血しない。
※シラミとハジラミを肉眼で見分けるのは難しい。毛に1㎜以下の白っぽい卵が付着していることもある。基本的に単体で寄生している状態はまれで、気づいた時には多数寄生していることが多い。
ノミ・マダニによる犬・猫の主な症状と健康への影響とは?

ノミやダニは、犬・猫にさまざまな症状を見せます。
ノミによる症状と健康被害とは?
ノミアレルギー/瓜実条虫/猫ひっかき病
ノミに噛まれると、ノミの唾液によるアレルギーで強いかゆみ・湿疹・脱毛が起こる「ノミアレルギー性皮膚炎」が見られることが多いです。一般的には腰背部や尾根部などに皮膚炎を起こすことが多く、激しく痒がります。室内でノミが繁殖することも珍しくなく、その場合、飼い主様の皮膚にも痒みが出ることが多いです。
ノミの体内には「瓜実条虫(うりざねじょうちゅう サナダムシの仲間)」が寄生していることがあります。犬猫の多くは体表のノミを気にして毛繕いをする過程で飲み込むことがあり、その際にノミの中にいる瓜実条虫が犬猫の消化管に入りこみます。条虫は腸管で成長し、やがて犬猫の便に卵を付けて排出します。正確には片節という体の一部で、中に多くの卵を含みます。ゆっくりと動く白ゴマのようなものが便の表面や肛門についていることで気が付きます。
また、バルトネラ菌をノミから媒介された猫が人間を「噛む・引っ掻く」などで傷をつくって感染すると、リンパの腫れ・頭痛・発熱が見られる“猫ひっかき病”のリスクもあります。
マダニによる症状と健康被害とは?
マダニは、犬や猫の体だけでなく、人間をも吸血します。
代表的なものが、SFTS(重症熱性血小板減少症候群)や日本紅斑熱、バベシア症、ライム病、猫ヘモプラズマ症といった感染症です。皮膚炎・発熱・食欲不振・関節の痛み・黄疸・下痢・嘔吐・皮下出血・貧血などさまざまな症状を見せます。
なかでも、SFTSは全国的にも感染するケースが増え、致死率も高いとして注意が必要です。
SFTS(重症熱性血小板減少症候群)について
この病気において知っておかなければならないことは、
・マダニに咬まれることで感染し、ヒトでの致死率が高い病気であること
・犬猫でも致死率が高い病気であること
・SFTSを発症した犬猫からもヒトに感染する病気であること
です。
SFTSとは?
近年、マダニに咬まれたことに起因して感染、発症するSFTS(重症熱性血小板減少症候群)の発生が多く報告されるようになりました。病原体はSFTSウイルスで、2011年に中国で初めて報告されました。2013年には日本でも報告がありますが、それより以前から野外に存在したと考えられています。正式な届け出があったものでいうと、日本でも1000件ほどの発生が確認されており、うち致死率は30%という非常に高いものとなっています。
ヒトはどうやって感染するのか?
ヒトは、マダニに咬まれたり、マダニを潰すなどした際に感染する可能性があります。時にはマダニに刺された痕が無くても、野外活動をした歴がヒントとなり診断されたケースも多くあります。
また、飼育している犬猫がSFTSに感染、発症した場合は、犬猫の体液から感染する危険が高く注意が必要です。体液、特に唾液にはウイルスが大量に含まれ、飛沫として飛んだり、触れた手であちこちを汚染してしまったりと、一般家庭での感染防止は困難と言えるでしょう。感染動物に触れる際には、ゴーグル、サージカルマスク、フェイスシールド、帽子、長袖ガウン、手袋を装着する必要があります。発症したペットから感染したり、ペットが持ち込んだマダニに咬まれるなどして感染したり、ペットが関係して感染してしまう懸念があるのです。
2025年に入って、SFTS感染猫を診察された獣医さんが亡くなられています。また西日本に多いとされていたこの病気ですが、おなじく2025年茨城県で猫のSFTSが発生しています。北海道でもSFTSウイルスを持つマダニが見つかっており、日本中どこで発生してもおかしくない状況にあります。
ヒトや犬、猫が発症するとどうなるのか?高い致死率!
ヒトがSFTSを発症した場合の致死率は30%くらいと言われています。潜伏期間は6-14日間で、発熱、倦怠感、頭痛などの症状で受診することが多く、リンパ節腫大や下痢嘔吐がみられることも多いようです。重症例ではウイルス血症、炎症、免疫不全などの重篤な合併症を起こし、多臓器不全などにより死亡する可能性があるようです。特に高齢者はリスクが高いとされています。
動物では特に猫に感受性が高く、その致死率は60%程度と言われています。(犬では40%以上) 野外に行く猫であり、マダニの寄生がある猫が、食欲元気低下、下痢嘔吐、発熱、黄疸などの症状を呈した場合は注意が必要です。SFTSを発症した猫の症状は急速に悪化し、数日以内に命に関わることがあります。また特効薬もないため、感染させないことが非常に重要と言えるため、基本的に外に出さないということが最も重要です。
万が一、愛犬、愛猫がマダニに刺された後に、体調が悪くなったら?
必ずあらかじめ動物病院に電話連絡し、マダニに刺されたことなどを伝えた上で、受診の相談をしてください。受診する際はウイルス飛沫が飛散しないようにキャリーをビニールなどで覆い、病院の外で支持を待つようにしましょう。飼い主様もメガネ、グローブ、マスク、消毒など、可能な限りの防護をし、心配かとは思いますが、なるべく犬猫に触れないようにして下さい。
なぜSFTSが拡がったか?
野生動物による伝播が主に考えられています。SFTSウイルスは、ウイルス保有マダニに咬まれた動物の体内で増殖します。特にシカやイノシシなどの野生動物は致死的な経過をとらず、体内でウイルス血症を発症して、大量のウイルウをため込んだ状態となります。それらの野生動物の血液を新たなマダニが吸血することで、ウイルス保有マダニが増えているとみられます。都市部でも野生動物は河川などを伝って活動域を拡げています。当院所在地の川崎市でも、ハクビシン、アライグマ、タヌキ等が生息しているため注意が必要です。
マダニ予防薬の役割とは?
動物病院で処方されるマダニ予防薬は、マダニがペットの血を吸血すると、短時間で駆除するといったものです。その為、吸血そのものを予防することは難しく、SFTSの感染を完全に阻止できるものではありません。多少の忌避効果があるものもありますが、万全な対策とは言えないのが現状です。動物たちの体をよく観察する習慣をつけ、吸血前に取り除けるようにしましょう。(その際には、飼い主様に寄生しないよう注意が必要です。)
今できる大切なことは?
マダニは吸血するとたくさんの卵を産んで数を増やします。大切なことは、公園やお散歩コースにマダニを増やさないことです。マダニ予防をするペットが増えれば、マダニ自体を減らすことにつながり、その寄生リスクも下げられるかもしれません。「マダニ予防薬を付けてもどうせ咬まれてしまうのなら意味がない」といって予防しないことは、将来的なマダニの数を増やしてしまうことにつながる恐れがあるかもしれません。そして、ペットたちや地域猫がマダニを拡げているんだという誤った風評被害が出ないよう、私たちが責任をもって犬猫たちを守ってあげる必要があるのです。
SFTSを発症したペットから人間が感染するという悲しい事例を少しでも無くすために、飼い主様ひとり一人の対策がとても大切です。
ノミやダニがついたペットの仕草とは?
被毛のなかに埋まったノミやダニは飼い主様も気づきにくいかもしれません。
ただ、犬や猫にとっては「痒い・痛い・違和感がある」などから、サインを見せていることがあります。
代表的なのは、
・しきりに体の一部を気にしている
・頭を振りまくる(ミミヒゼンダニの可能性)
・体を床に擦っている
・眠っている途中、急に起き上がる
などです。
マダニに関しては、眼や耳の周りなど、毛が薄い場所に寄生していることが多く、1匹から数匹以上付着している場合があります。吸血すると大きく膨らむため、飼い主様が気付くケースが多いです。
ペットを守るためのノミ・ダニ予防法・正しい対策方法はコレ!
ノミ・ダニの予防や対策についてご紹介していきます。
動物病院で処方された予防薬を使う
市販の予防薬もありますが、動物病院で処方してもらうお薬を使用したほうが確実な効果という面で安心でしょう。また、正しい使用方法も指導してくれますし、直接処置してもらうこともできます。予防薬は、基本的に強い副作用はなく安全です。飲み薬タイプや滴下タイプ、1カ月から3カ月以上効力の続くタイプなど、様々なものが処方可能です。
ほかの犬や猫との接触も気をつける
外出先で他の犬や猫と接触し、その後に付着するケースもあります。猫の場合は、外に出ないようにすればある程度防げますが、多頭飼いの場合は他のペットからもらってしまうこともあります。
また、飼い主様が外で野良猫と触れ合うのもNGです。
野良猫はノミやマダニがつく可能性が高い暮らしをしているため、ついているケースも多いでしょう。飼い主さんが野良猫を撫でた際にノミやマダニをもらい、それを家に持ち込む可能性もあるため注意しなければなりません。
散歩が終わったらペットの体のお手入れを
散歩から帰宅したらブラッシングで取り除けるようにしましょう。特に、草むらで散歩した後は丁寧に体をチェックすることが大事です。
日常的にお部屋を掃除して環境を整える
犬や猫がふだんいるスペースや、いつも使うタオル・シーツなどを丁寧にお手入れしましょう。特に、カーペットは卵が潜んでいる可能性もあります。
掃除不足のところに犬や猫が寝そべって寄生されるリスクもあるため、定期的に掃除を徹底しましょう。

ペットがノミ・ダニに寄生された場合の適切な駆除と治療方法
「犬や猫にノミ・ダニがいる…!」と見つけるとびっくりしますよね。愛犬や愛猫がノミやダニに寄生されたときの駆除や治療について見ていきましょう。
ノミを見つけたとき
ノミは動きも素早く、1匹や少数では気づきにくいため、飼い主様が発見するときは大量というケースもあり、かなり驚くかもしれません。
びっくりしたからと言って、素手で潰して除去するのはNGです。もしメスなら卵が散乱し、それが孵化して再び増殖します。自宅でシャンプーして洗い流そうとしても、完全に駆除することは不可能です。
また、市販の駆除薬では中途半端効果しか得られず、再度ノミの増殖に苦しむことになります。しっかりと駆除するため動物病院で見てもらいましょう。
マダニを見つけたとき
犬や猫の皮膚で“血を吸っている”マダニは、大きく膨らんで見つけやすいかもしれません。そこで注意したいのが「無理に取ろうとしないこと」「つぶさないこと」です。
吸血中のマダニは、動物の皮膚に顎を固定しているため、飼い主様が無理やり引き剥がそうとすると皮膚内に顎が残るケースが多いです。マダニを取っても強いかゆみの症状に犬や猫は苦しみます。
また、ウイルスなどの病原体をもっているマダニの場合、潰されたことで病原体が飛び出し、それが飼い主様に感染する恐れもあるため注意が必要です。動物病院なら感染対策をした獣医師が専用のピンセットできちんと取り除いてくれます。
マダニを見つけたときは、自己流で対策するのはやめ、動物病院で駆除してもらいましょう。
ノミやダニが寄生したら、まずは動物病院で診察を
寄生虫がついた場合の基本的な治療は“駆除すること”です。
駆除薬にはいろいろな種類があります。使ってから数時間で効果が出始めるものが多いです。
市販のノミやダニ対策の薬もありますが、「体に入って作用する医薬品」ですから自己判断での投与は危険です。ペットの体調によっては、安易な判断での市販薬がかえって健康被害を及ぼすケースもあるため注意しましょう。

まとめ
ノミやダニは小さな生物なのに、寄生されることによって皮膚トラブルや感染症のリスクがあります。ノミやダニが活発になる時期にあわせて予防薬で対策することも可能です。
また、外から知らず知らずのうちに室内に持ち込むと、繁殖力も高いノミやダニの卵が孵化して増えることもあります。肉眼では見えづらいため、「体を痒がっている」「食欲がなくなっている」「皮膚に炎症が起きた」などの症状が犬や猫に現れたら動物病院を受診しましょう。
ノミやマダニが体についたのを発見したときも、自己判断で取らずにすぐに獣医師に相談することをおすすめします。
そして、SFTSなどの恐ろしい感染症から、ペットたちや私たち人間を守らなくてはなりません。
竹原獣医科医院では、今年からより一層ノミ・マダニ予防に力を入れてまいります。飼い主様には、ご家庭の全ての犬猫達に、ノミ・マダニ予防を実施するようお願いいたします。また、地域猫に関わっておられる方は、可能な限り野外の猫たちにもノミ・マダニ予防剤の使用をお願いいたします。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |