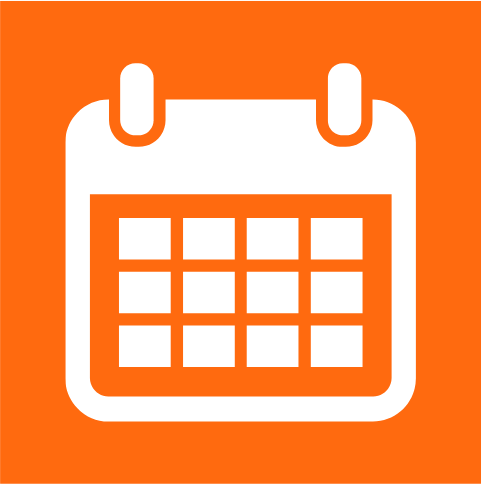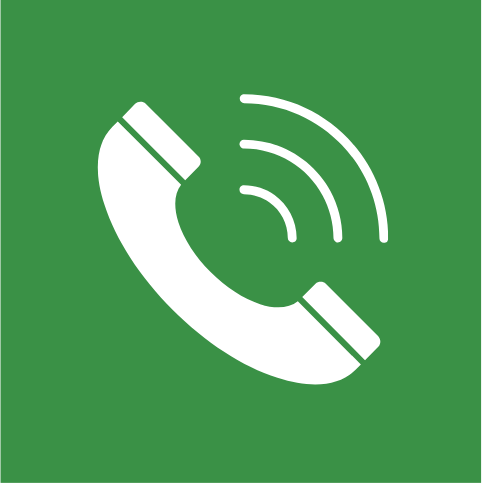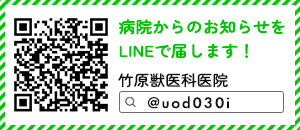糖尿病は犬猫の恐ろしい病気!?メカニズムから発症のサイン、糖尿病の治療から予防までを解説!2025.08.19

犬や猫も人間と同様に糖尿病にかかる動物です。特に、年齢を重ねるにつれて糖尿病を発症しやすい傾向ですが、若くても発症することがあります。初期症状はあまり見られないことから、気づくのが遅くなることもあるため、早く発見することが大切です。
糖尿病と診断されたらとても不安ですが、治療方法も確立されているので、飼主様が正しく向き合うことで愛犬や愛猫の元気も取り戻せるかもしれません。
「最近、よく水を飲む」「おしっこの回数が多いのでは…?」「ご飯を食べているのになぜ痩せるのだろう?」など犬や猫の糖尿病のサインもあります。
今回は、犬と猫の糖尿病の症状や発症原因、治療法や予防法にいたるまで分かりやすく解説していきます。
目次
犬と猫の糖尿病とは?水をよく飲む・尿が多い時に疑うべき病気のサインを解説
はじめに、犬と猫の糖尿病の特徴や、糖尿病になった時に見られるサインをご紹介していきます。
糖尿病のメカニズムは?
糖尿病とは、インスリンの量不足または作用不足が引き起こす高血糖と、それに起因する代謝異常によってさまざまな病態を引き起こす症候群のことをいいます。
簡単に言うと、「おしっこに糖が出てしまうくらい血液中にブドウ糖が増えている状態が続くと、命に関わるほど体に良くない」ということです。
ブドウ糖は、食べ物(主に炭水化物)から得られ、細胞が必要とするエネルギーとなります。そのためブドウ糖は常に、血液によって全身に運ばれ、細胞に取り込まれ利用されています。そのためにはブドウ糖は、血液から細胞に移動する必要があります。そこでインスリンというホルモンの作用により、ブドウ糖が細胞内に取り込まれ利用されるのです。
インスリンと聞くと何やら注射の名前というイメージをお持ちの方も多いと思いますが、本来は人を含む動物がもともと持っているホルモンなのです。インスリンは膵臓のβ細胞から分泌されています。
糖尿病は血液中にブドウ糖が沢山ある状態のことを言います。それはインスリンが分泌されなくなったり、インスリンが正しく働かなくなったりすることで、ブドウ糖が細胞に取り込まれなくなることを意味します。つまり、「血液中にはブドウ糖は沢山あるのに、細胞にはそれが届かなくなる病気」ということになります。エネルギーを利用できないことで、体はそれをカバーするために代謝の経路を変えて対応しようとし、それが最終的には悪影響を及ぼすのです。
犬と猫の糖尿病とは?
犬も猫も、7歳を超えた中高齢になってくると比較的多く発症する病気です。
犬はメスが糖尿病を発症しやすいのに対し、猫はオスの発症率が高めとなっています。
また、糖尿病には、
・体内でインスリンが分泌できず不足する「Ⅰ型糖尿病」
・インスリンは分泌して十分あるのに機能しづらい「Ⅱ型糖尿病」
と大きく2つに分けられます。
犬の場合は前者の「Ⅰ型糖尿病」が多いのに対し、猫は後者の「Ⅱ型糖尿病」が多い傾向です。
糖尿病のサインとは?
次は、糖尿病のサインとして見せる症状について見ていきましょう。
①水をたくさん飲む
「ふだんよりも飲水の回数が多い」「お水をずっとぴちゃぴちゃと飲んでいる」などは、糖尿病でよく見せる症状です。糖尿病になるとおしっこがたくさん出て体が“脱水”となり、それを補うために水をいっぱい飲みたがります。
②排尿の回数が増える、排尿の量が多い
血糖値が高いと利尿作用が働き、尿量が増えます。尿の量が増えるため、一回のおしっこの量が増え、回数も増すことで、1日の尿量が明らかに増えます。⓵と②の症状を合わせて「多飲多尿」といい、糖尿病のケースではほとんどがこの症状を発症します。
また尿に糖分が出るため、尿がべとついたことに気付く方もいます。時には膀胱炎により頻尿や血尿を起こすこともあります。
③普通に食べているのに体重が減る
いつもと変わらず食事をしているのに体重が減ってくるのも糖尿病の症状です。
ふだんと変わらない食事量だと、飼主様としては「食欲が普通にある」と感じるかもしれません。
糖尿病になると、高血糖により食欲はむしろ増す傾向もあるので注意が必要です。
です。体としては「ご飯を食べてエネルギー補充」しているものの、インスリンの作用が足りなことで、細胞がエネルギー利用することができず、「細胞がお腹を空かしている状態」というわけです。これにより体重が増えず、逆に減少するのです。
④目が白く濁ってくる(犬の場合)
犬の場合、糖尿病になると白内障になることがあります。目が白く濁って視力が落ちるのも糖尿病のサインです。
体の血液に糖が増えると、目の“水晶体”にも糖が含まれてダメージを受けます。水晶体が変性し白くなって視力も落ちてくるケースも。糖尿病による白内障の場合、急激に進行することや、両目が同時に発症することもあります。
猫の場合は糖尿病による白内障が起こることはあまりありません。
⑤毛のツヤがなくなる
インスリンの働きが悪くなる糖尿病になると、栄養素を細胞に取り込むことができません。血流も悪くなり皮膚状態も悪く、毛のツヤがなくなり毛並みは悪くなります。
皮膚も乾燥するので被毛のパサつきと一緒にフケが出やすいです。抜け毛が多い、パサパサした被毛、ツヤがないといった毛の変化が見られるでしょう。
また、猫の場合は通常はグルーミングの習慣があって、自分で毛を舐めて整えようとしますが、糖尿病になると毛づくろいをしなくなります。
⑥足のふらつき(猫の場合)
足に力が入りづらく、歩く際にふらついたり、座るような姿勢で歩くケースもあります。かかとを床につけて歩くような姿勢となり、これを蹠行(せきこう、しょこう)といいます。糖尿病による末梢神経障害から、一部の猫に発症します。これは治療と共に改善することが多いです。
初期症状はあまりないけれど…
糖尿病は進行が緩やで、初期には症状がほとんど見つけることはできません。
少し進行すると「水の量が多い・おしっこが多い」などの症状を見せるようになります。多飲多尿や体重の減少などはふだんの健康観察をしていると気づきやすいポイントです。
また、末期になると
・食欲不振、あるいはまったく食べない
・体重減少が著しい
・尿が出なくなる
・下痢や嘔吐
・けいれん
・ぐったりする
・呼吸が速くなる
・動かなくなる
など明らかに体調に異変が起こります。
糖尿病は進行して重症化しないように、ちょっとした体の異変に気づいたら動物病院で受診することが大事です。
犬と猫の糖尿病の発症原因|遺伝や肥満、膵臓関連などリスク要因を解説

次に犬や猫の糖尿病の原因となるものを見ていきましょう。
加齢、肥満など人間と共通する原因も
加齢、肥満、生活習慣などにより発症することが多い人の糖尿病は、Ⅱ型糖尿病と言われ、犬猫にも見られます。犬や猫は7歳頃にはすでに“シニア”です。体の動きも若い頃とは違い、ホルモンのバランスも乱れる頃。加齢とともに運動量が不足して太りやすくなり、糖尿病にかかることもあります。
「このごろ太ってきたかな…」と見た目の変化を感じたら、もしかしたら糖尿病のリスクがあがっているのかもしれません。
一般的に去勢手術、避妊手術を受けると体重は増えやすくなりますので、体重管理を怠り肥満体型になってしまった結果、糖尿病リスクが高くなるケースもあります。しかし、去勢・避妊手術によって防ぐことのできる病気がたくさんあり、メリットも大きいため、糖尿病への心配から手術をしないということはお勧めできません。避妊手術が糖尿病予防になる場合もあるので、次で説明します。
ホルモン異常が関係することも
避妊手術を受けていない犬では、発情や妊娠などによるホルモン分泌の変化(高プロジェステロン)により、糖尿病となるケースがあります。この場合、治療として避妊手術の実施を検討する必要がります。
クッシング症候群、先端巨大症などによるホルモン過剰が、インスリンの働きを阻害して、糖尿病となるケースがあります。特にクッシング症候群は犬によくみられるホルモン病で、様々な症状を示すなかで、その一部が糖尿病を併発します。しかし猫では、糖尿病を発症して初めてクッシング症候群の診断がつくケースも多ようです。これらの疾患の場合は、ホルモン病の治療とインスリン注射による糖尿病治療の両方が必要になる可能性が高いでしょう。
免疫異常や遺伝が原因となることもある
犬では免疫異常によりインスリン分泌細胞が破壊され、糖尿病になるケースも多くあり、これは人でいうⅠ型糖尿病にあたると考えられています。猫ではこのタイプは稀とされています。
遺伝的には猫の場合、バーミーズやメインクーン、アメリカンショートヘア、シャム猫などが糖尿病にかかりやすいとされています。犬の場合は、ミニチュアシュナウザーやトイプードル、ビーグル、ダックスフンドなどが比較的糖尿病のリスクが高いと言われています。
そのほかに原因不明のものもあります。
糖尿病と膵臓との関わりとは?
糖尿病と膵臓との関わりも大きいです。
膵炎によってインスリンを作る細胞がダメージを受けて糖尿病になることもあります。
体内で
・食べたものを分解・吸収する
・インスリンを分泌する
といった大きな役割を持つのが「膵臓」です。そこで炎症が起こると、インスリンを分泌するβ細胞が減少したり、障害されたりします。炎症が強い、または長期にわたるなどで、膵臓β細胞がダメージを蓄積させていくと、糖尿病を発症してしまうかもしれません。
特に慢性膵炎は、糖尿病を発症すること多い病気です。食欲不振や嘔吐下痢などの症状から膵炎が疑われることもありますが、なかには無症状で膵炎を発病しているケースもあります。
特に猫では慢性膵炎の有病率が高く、症状も様々なことから、見落としがちな疾患です。
いずれにしても、血液検査や超音波検査で発見できるケースもありますので、気になることがあれば早めの診察をおすすめします。
犬と猫の糖尿病の治療方法
「愛犬や愛猫が糖尿病かもしれない…」と考えるととても不安ですよね。治療に正しく向き合えば、ペットの穏やかな生活を守ることができます。それでは、どんな治療方法があるのかご紹介します。
動物病院ではどんな診断をする?
動物病院では、まずは飼主様からの問診から糖尿病の可能性を考えます。糖尿病のサインとなる「飲み水の量・尿の回数・体重の減少・食欲の変化」などは受診の際にメモしておくとスムーズです。
血液検査で血糖値を測定し、普通よりも数値が高いと糖尿病の可能性があります。ただ、血糖値の数値は、興奮や大きなストレスがかかると一時的に上昇することがよくあります。
そのため、「血糖値が高い=糖尿病」とは断定できません。当院では基本的に以下の項目をもって糖尿病と診断します。
・血糖値が高いこと
・尿検査にて尿に糖が出ること
・血液検査にて、糖化アルブミンやフルクトサミン値を測定し、
2週間程度の血糖値の目安を調べ、持続的高血糖を確認すること。
(・犬の場合、さらに詳しい評価の為、インスリン濃度を測定する場合もあります。)
治療の前に
糖尿病の診断がついたら治療となりますが、その際にとても重要なことがあります。それは
全身状態の把握、すなわちその動物の重症度がどの程度のものかということです。
犬猫の糖尿病では、発症から比較的時間がたっていない症例では、比較的良好にコントロールできる場合が多いです。入院が必要ないことも多いですが、インスリン注射は必要になる場合が多い為、血糖値の推移をみるために検査入院をすることもよくあります。
病状が進行したケースでは、代謝異常により尿中にケトン体という物質が検出されることがあります。ケトン体が出ている状態は糖尿病性ケトアシドーシス(DKA)という危険な合併症を起こした状態と言えます。また特に猫の場合は高浸透圧高血糖症候群(HHS)を起こすこともあります。
DKA、HHSなどの合併症は、糖尿病治療において非常に予後の悪い危険な状態と言えます。点滴やインスリン投与はもちろん、カリウムやリンの補充、経鼻カテーテルからの給餌など、たくさんの検査や処置、薬剤治療が必要となり、入院は少なくとも1週間以上となる可能性があります。そしてこれらの治療を行っても命を落とすケースがあるのです。
糖尿病は人でいう生活習慣病のイメージがありますが、ひとたび体の代謝の歯車が狂い悪循環となると、命に関わる恐ろしい病気です。犬猫が糖尿病となり、DKAやHHSなどの合併症を起こしているとわかったら、飼い主様はその病状がとても重篤であるということを理解する必要があるでしょう。
治療方法とは
ここでは合併症を起こしていない場合の糖尿病の治療について解説します。
インスリン療法
糖尿病になったら基本的には「インスリン」を補充する治療が行われます。1日1~2回、インスリン注射を長期的に行って治療をする方法です。
多くの場合、糖尿病と診断されてインスリン注射を始めたら一生行います。ただ、猫の場合は稀にインスリンの安定によって注射がいらなくなるケースもあります。
注射は飼主様が自宅で行うため、不安に思うかもしれません。獣医師に不安な点は相談し連携しながら、愛犬・愛猫の治療を進めていきましょう。
食事療法

食事の内容と量をコントロールするのも糖尿病治療では大切です。「低炭水化物・高たんぱく」が糖尿病治療には効果的で、動物病院では治療用の療法食が推奨されます。市販もされていますが、獣医師に相談しながらフード選びをすると安心です。
体重療法
糖尿病を治療していくうえで気をつけなければならいのが「太り過ぎないこと」です。
体重が増えるとインスリン注射が効きづらくなるため、適度に運動をして体重をコントロールすることも大切です。ただ、運動をし過ぎると血糖値の急上昇にもつながるため、無理のない範囲で運動を行いましょう。
基礎疾患の検査
糖尿病治療がインスリン投与などにより安定した場合もそうですが、特に安定しない場合は、その原因となっている他の病気がないかを探す必要があります。
・クッシング症候群、先端巨大症などのホルモン疾患
・未避妊犬などにおける性ホルモン過剰
・膵炎や三臓器炎(猫)などの膵臓関連疾患
・脂質代謝異常
・その他の炎症性疾患、腫瘍性疾患など
糖尿病を予防するためには
犬や猫が糖尿病にならない予防策をご紹介します。
体重の増加に注意する

ぽっちゃりしている犬や猫は可愛らしい雰囲気ですが、健康的とは言えません。糖尿病だけでなく、さまざまな病気の原因にもなり得ます。
食事量は適量を与えることや、適度な運動をさせることなどで糖尿病の予防につなげましょう。
室内で暮らす猫の場合、犬と違って「散歩」という運動がありません。キャットタワーやおもちゃなどで一緒に遊んであげると体重管理につながります。
一緒に遊ぶことは、体重管理もできてストレス解消にもなります。
定期的な健康チェックを行う
シニアの犬や猫は糖尿病のリスクが高まってくるので、健康診断がおすすめです。動物病院では、犬や猫の健康診断として血液検査や尿検査を行うことができます。
糖尿病は初期にはほとんど症状を見せません。そのため、定期的な検診によって愛犬・愛猫の健康チェックを行うことで早期に発見できるケースもあります。
通常は年1回程度、シニアになったら年2回の健康診断が理想です。
まとめ~大切な家族の健康を守るために
ペットの健康と暮らしを守れるのは飼主様だけです。愛犬や愛猫の健康チェックノートなどを書き込むことで、日常的な変化に気づきやすくなります。何らかの異変があれば早めに動物病院で診てもらうことも大事です。
犬や猫の糖尿病は比較的多い病気です。そのため、治療方法もあり、動物病院で早期に診断してもらったうえで正しい治療を受けることができれば、愛犬や愛猫の健康的な暮らしを守れるでしょう。
少しでも異変を感じた場合は、自己判断せずに川崎市の竹原獣医科医院までお気軽にご相談ください。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |