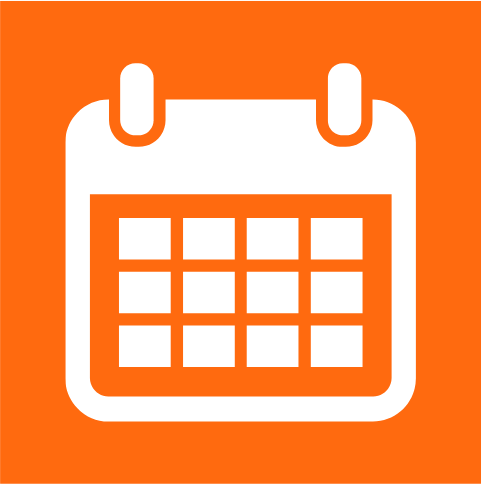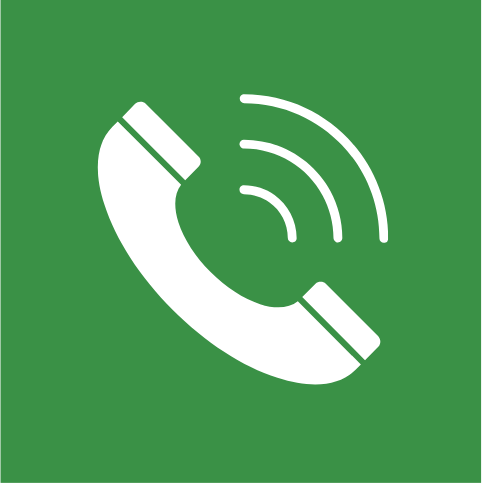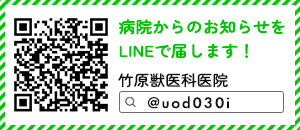猫の慢性腎臓病の治療法とは?進行予防のために、最善の治療を選択しましょう。2025.05.02

猫にとって腎臓病は宿命的な病気でもあり、シニアになるとかなりの確率で腎臓が悪くなると言われています。
一般的に傷んだ腎臓を治すことは難しいとされています。人でも、慢性腎臓病が進行すると、人工透析※が必要となる現状があり、腎臓を治すことがいかに困難であるかを物語っています。猫の場合も同様で、慢性腎臓病により腎組織がダメージを受けて続けてしまうと、その部分が治ることはないのです。そして、徐々にその範囲は拡大し、最終的には腎不全となってしまうのです。
(※人工透析:老廃物や余剰水分などをろ過、排泄するといった腎臓の機能を、機械で人工的に代替えする治療法です。老廃物がたまる「尿毒症」にならない為の治療ですが、腎臓を治しているわけではありません。)
では、高齢になると高い割合で慢性腎臓病を発症する猫のために、何かしてあげられることはあるのでしょうか?そして、すでに慢性腎臓病であると診断された猫に対して、治療法は全くないのでしょうか?
前回は、腎臓病の早期発見のためにできることをご紹介しましたが、今回は、実際に猫の腎臓のためにできること、そして、腎臓病になった際の治療法について解説します。
腎臓病のメカニズムや、早期発見の大切さ、早期発見のための方法については、前回の記事で解説していますので、あわせて読んでみてください。
目次
「シニア期」・「腎臓病“初期”」にすべきこと
猫のシニアは7歳から
猫の平均寿命は16歳前後と言われていますが、20歳を超える猫も少なからずおり、実際には大きくばらつきがあります。猫の品種や室内飼育かどうかによっても違いがあるでしょう。ある日の診察中、12歳の猫ちゃんの飼い主様に、「高齢になってきましたね」と言ったところ、「まだそんな年じゃないわよ~」と返されて、お互いに驚いたことがあります。
しかし、シニア期は7歳ころからと言われています。猫の12歳は60代半ばといわれていますので、高齢と言っても失礼に当たらないとは思います。ただ、20歳まで生きた猫がいた家だったりすると、猫の12歳はまだまだ中年程度と思ってしまう気持ちもわかる気がしますし、確かに人の65歳はまだ若いですが、色々な病気が出てもおかしくない年齢と言えると思います。
「まだ若い!」という思い込みは、慢性腎臓病の早期発見ができなくなる、大きな落とし穴になってしまいます。まだ若々しくいてほしい気持ちはあっても、「そろそろ検診を受けないといけないな…」という認識が必要な時期に来ているのです。
シニア期の検診で「異常なし」となったら
シニア期の猫の場合、検診で腎数値などに異常がなかった場合、飼い主様はほっと胸をなでおろすことでしょう。しかし、血液検査のBUN、CRE、リンなどの項目は、初期の腎臓病では上昇しないことが多く、明らかに上昇した頃には腎臓組織の7割以上が障害を受けています。(前回記事参照)
結果が異常なしであっても、以下のことを行うことが大切です。
・半年おきに検診を継続する
(1年で5年分の歳をとるので、人でいうと、2-3年ごとに検診していることになります)
・より詳しく、早期マーカーなどで評価する
・自宅で飲水量や体重測定を行うなど、早期発見のための習慣を始める
・腎臓病は始まっているものと見込んで、フードやサプリなどの対策を始める
早期発見のためにすべきことは、前回の記事を読んでみてください。実際に腎臓のためにできることを次に紹介します。
当院がおすすめする食餌療法とフード

シニア期・慢性腎臓病初期
フードには獣医師専用の処方食(療法食)があります。いわゆる腎臓食として「腎臓〇〇〇」、「キドニー〇〇」など、腎臓のキーワードが入った処方食がたくさん存在します。それだけ腎臓病の猫は多いのです。また食欲の落ちやすい猫に配慮して様々な味や形が用意されています。腎臓病食はタンパク質制限が強いため、初期の慢性腎臓病の猫には適応にならず、かえって筋力低下などを助長してしまう可能性があるかもしれませんのでご注意ください。
本来これら処方食は、獣医師が診察した猫に対してのみ使用すべきものなのですが、実際は、量販店での販売やフリマサイトなどでの転売が行われている現状があります。これでは、腎臓病食がまだ必要でない猫に対して与えるなどといった、間違えたフードの使い方をしてしまうリスクが心配されます。
初期の慢性腎臓病の猫や、検診でBUN、CREに上昇の無いシニアの猫には、「早期」「初期」などの言葉が入ったものや、シニア期専用のフードがおすすめされます。また近年では腎臓の老化を防止したり、障害から守ったりというサプリメント要素を兼ねたフードも販売されています。オメガ3脂肪酸やAIM研究から開発されたフードもその一例で、これらも選択肢の一つとなるでしょう。
慢性腎臓病中期以降
IRISステージ3以降に相当する状態であれば、食欲にもムラが生じたり、同じものをずっと食べてくれなくなったりしている可能性もあります。基本的には腎臓病用の処方食のみを与えていただくことをおすすめします。当院では常時、8社前後のメーカー、種類にして約20種類の腎臓食サンプルをご用意しておりますので、お気軽にお試しいただけます。
また、あまりにも食べない場合はそれで栄養不良になってしまう恐れもあります。トッピングとして、腎臓に配慮したトリーツを使用することもおすすめしています。それでも食べてくれない場合は、一般食にサプリメントなどを混ぜて与えることもやむを得ないかもしれません。
当院がおすすめするサプリメント
治せない病気だからこそ、サプリメントはとても大切
サプリメントにもたくさんの種類があり、当院でも複数のサプリメントを使用しています。
お薬は、その効果に対して多くのデータがあり、承認が取れたものです。しかし承認が取れるまでの工程には多くの時間と費用が掛かるため、実用化されている種類が少なく選択肢が限られています。また副作用という面でも問題になる場合があります。
一方世の中には腎臓に良いとされる物質もたくさん見つかっています。それらはお薬のように実証された強い効果は無くても、腎臓にとって良い調査結果が得られているものがあり、サプリメントとして使用されます。またサプリメントはお薬ではないので、副作用が少ないことが一般的です。
当院では飼い主様と相談しながら、腎臓の状態、飲めるかどうか、費用などを加味して、どのサプリメントをしたらよいのかを決めるようにしています。その例をご紹介します。
・5-ALA…体のすべての細胞がエネルギーつくり機能するのに欠かせない「ミトコンドリア」。これを活性化する世界初のサプリメントです。人ではコロナウイルス感染症流行時に大きな話題となりました。動物では、腎臓病を筆頭に、痴呆症や高脂血症、肥満などにもひろく用いられています。当院では過去に、このサプリメントを慢性腎臓病の動物に使用した臨床試験を実施しました。 製品名:エネアラ
・アミノ酸…アミノ酸はタンパク質を分解して得られる栄養素です。腎臓病のフードはタンパク質制限がされているものがほとんどですが、アミノ酸自体は体にとってとても重要です。特にアミノ酸の中には腎機能を温存する効果を持っているものがあり、それらをしっかり補給することで、血清CRE値の低下や、体重および筋肉量の減量防止に役立つことがわかっています。 製品名:アミンアバスト
・リン吸着剤…血清リン値が正常値であっても、体内でのリンの蓄積は始まっていると考えられ、慢性腎臓病初期のFGF-23値をみても、比較的早い段階からのリン制限は有効と考えられます。食餌中のリンを吸着することを目的とし、無味無臭の粉末サプリメントを食事に混ぜて与えます。これによりFGF-23値の低下をみた症例もいます。当院では過去に、このサプリメントを慢性腎臓病の動物に使用した臨床試験を実施しました。 製品名:リンケア、カリナールコンボ
・オメガ3脂肪酸…慢性腎臓病に代表される多くの病気は、老化現象と関連します。老化の原因の代表として「酸化」があり、抗酸化作用や抗炎症作用のあるオメガ3脂肪酸は、人の分野でも注目されてきました。当院では、良質なオメガ3脂肪酸やミドリイガイ成分を配合したサプリメントを、腎臓病に限らずすべてのシニア動物におすすめしています。 取扱実績製品名:アンチノール、アンセット、モエギタブなど
・乳酸菌…乳酸菌製剤は、腸内細菌叢のバランスを整え、良好な便形状を作るだけではなく、免疫調整機能や腎臓病抑制効果を持っています。腸内環境に悪玉菌が増加すると、腎臓の負担になったり、尿毒素が増えたりして、腎臓に負担をかけると言われています。シニア期や慢性腎臓病初期はもちろん、若いうちから善玉菌を摂取することは、腎臓だけではなく体全体にとって良いことなのは間違いないでしょう。
取扱実績製品名:マイトマックス、フォーティフローラ、アゾディル、カリナールコンボ、コスモスラクトなど
この他にも様々なサプリメントがあります。当院では、人で効果があるとされている成分を猫用に製品化する際の臨床試験も多く行ってきました。今よりももっと良いもの、効果的なもの、その子に合ったものが、今後見つかるかもしれません。
当院が実施している投薬治療
「腎臓治療といえば点滴」とイメージされる方も多くいらっしゃると思います。当院にも、腎臓の診断がついたら、「自宅での皮下点滴を始めた方が良いですか?」と質問される方もいらっしゃいます。点滴治療は脱水の徴候が見られたら行いますが、そうでなければ過剰な水和により体に負担をかける場合もあります。当院では、食事療法、サプリメントにつづき投薬治療により、腎臓病の進行を可能な限り抑えるような治療を実施しています。
・ベナゼプリル(ACEI) 「フォルテコール」
ACE阻害薬とよばれる薬です。血圧降下作用により全身の血圧低下および腎糸球体内圧を低下させ、ネフロンを温存し腎保護作用を示します。血圧をコントロールすることで、腎臓の最も大切な組織であるネフロンという器官を守り、さらなる障害から腎臓を守るお薬です。
・テルミサルタン(ARB) 「セミントラ」
蛋白尿抑制と血圧降下により、腎機能を保護するお薬です。目的によって2種類の製剤が使用されます。シロップですので、猫ちゃんによっては飲ませやすいかもしれません。
・べラプロストナトリウム 「ラプロス」
糸球体障害、炎症、微小血栓による虚血などを抑制し、腎組織の線維化(硬くなって働かなくなる状態)を予防するお薬です。また食欲が落ちにくいという猫もいるようです。
・アムロジピン
血圧降下剤です。
・活性吸着炭
尿毒症治療に用います。
・食欲増進剤 「ミルタザピン」「エルーラ」
腎臓病は食欲低下をおこす疾患です。腎臓病との長い付き合いの中で、体重減少は大きな問題となります。補助的な治療として、食欲増進剤を勧めることがあります。

当院が実施している点滴治療
点滴をする目的は?
腎臓病治療で実施される点滴で使用する製剤は、ラクトリンゲルや生理食塩水などが用いられます。これは主に水分や電解質が主体であり、その目的は、細胞周囲と血液循環への水分補給、アシドーシスというバランス乱れの補正などです。そこにビタミン剤などの薬剤を添加して投与される場合もあります。
しかし、飼い主様の中には、「点滴しているから栄養が摂れている」と勘違いされている方も少なくありません。本格的な栄養素であるたんぱく質や脂肪分などはこれらの点滴では摂れないのです。これらは経口的に摂取しなければないこと、そしてそのことがとても重要であることを知っておきましょう。当院では、自発的な食欲がなければ食欲増進剤を使用し、それに反応しない場合は、シリンジなどを給餌したり、経鼻カテーテルなどで給餌したりすることを提案しています。
点滴治療は、栄養治療ではなく、体の水和とバランスを整えて体調の地盤をつくることにあります。さらに、慢性腎臓病が進行して上昇した尿毒素を下げる目的もあります。
食欲低下
元気消失
嘔吐
歯周病の悪化
筋肉量低下(悪液質)
脱水(皮膚の弾力低下、被毛のパサつき、目の落ちくぼみ)
便秘
頭を下げて動かない(電解質異常)
けいれん発作
これらの症状がみられる状態は、尿毒素が溜まった状態かもしれません。尿毒素とは、本来尿で排泄される老廃物のことで、腎臓の働きが落ちたことでこれが体にたまってしまうと、様々な症状を引き起こします。これらの症状を改善したり、予防したりするためにも点滴は重要な治療法です。
点滴の方法は?
一般的な方法として、静脈点滴(血管点滴)と皮下点滴を実施します。それぞれの特徴をいかに示します。
〈静脈点滴〉
血管点滴ともいわれ、四肢の血管に留置針というプラグを装着し、直接血管内に投与します。重症例には特に推奨されます。
メリット
・効果が高く即効性がある
・吸収不良などによる違和感や浮腫を起こしにくい
・ゆっくり長時間投与でき、尿量を見ながら無理なく多くの輸液剤を投与できる
・ブドウ糖やカリウムなどを投与可能
デメリット
・入院や預かりが必須である
・留置針というプラグを設置するため、エリザベスカラーが必要な場合が多い
・留置針は長期間使用できないため、数日ごとに交換する必要がある
(連続して同じ手足は使用しない)
〈皮下点滴〉
皮下補液ともいわれ、主に背部の皮の下に、一度にまとまった量の輸液剤を5分程度で注入し、その後徐々に吸収されていく方法です。
メリット
・簡便である
・通院で、かつ5分程度で実施可能
・長期的に継続可能である(ex.週2回で継続 など)
・維持期の尿毒症予防などに実施
・自宅で飼い主様が実施可能(※数回の指導が必要)
デメリット
・効果は静脈点滴より低く、重症例には向かない
・皮下に投与できない薬剤がある
・浮腫や感染などのリスクがある
このように、点滴の方法によりメリット・デメリットがあります。また、点滴自体が問題となる場合もあります。特に点滴の量が体にとって多い場合は過剰水和となり、浮腫や胸水など時として望ましくない事態を引き起こします。尿が既に作られなくなった腎不全末期状態(乏尿期)では、点滴はかえって猫に負担をかけてしまうかもしれません。低アルブミンや心臓疾患などにも注意が必要です。病状により推奨される点滴方法が変わりますので、担当の獣医師とよく相談して決めましょう。
番外編 AIMについて
AIM製剤は、腎臓病の治療に有効と期待されている新薬です。その発見から創薬は、「AIM医学研究所」「株式会社IAM CAT」の宮崎徹先生が中心となり、現在進行形で開発が進んでいます。当院は数年前より宮崎先生に全面的に協力しており、当院の患者様にもデータの提供など多くのご協力をいただきました。
飼い主様の中には、AIMを今か今かとお待ちになっている方もおられることでしょう。私どもも可能な限りの協力をさせていただき、1日も早いAIM製剤の普及を望んでおります。
AIMについては、前回の記事またはAIM医学研究所のHPをご覧ください。

まとめ
加齢とともに猫は腎臓病を発症しやすく、猫の宿命的な病気と言われています。
しかし、「予防策を実践した暮らし」と「何もしない暮らし」では病気のリスクも変わるものです。
飲み水や食事管理、定期的な受診による早期発見など、猫の腎臓病予防のポイントは飼主様の日頃のケアが中心となっています。大事な猫ちゃんの健康を守るために、ぜひとも腎臓病予防を実践してみてください。
また、慢性腎臓病は、ちょっとずつ進行するので、明らかに異変を感じたときには重症していることもあります。腎臓病になると多飲多尿や食事量減少、体重減少などの変化が見られるものです。
ひとくちに猫の慢性腎臓病といっても、その症状や治療方法は猫ちゃんによって十猫十色です。当院は慢性腎臓病の猫ちゃんに対して、多くの選択肢を提案できるよう、最新治療薬の研究に協力し、新開発のサプリメントも積極的に導入するようにしています。早期発見にも力を入れておりますので、猫ちゃんの飼い主様は、どうぞお気軽にご相談ください。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |