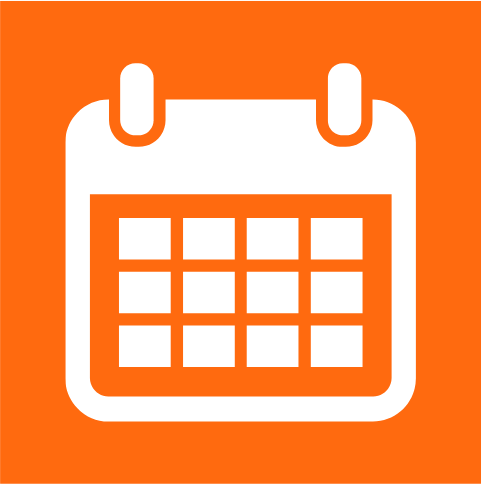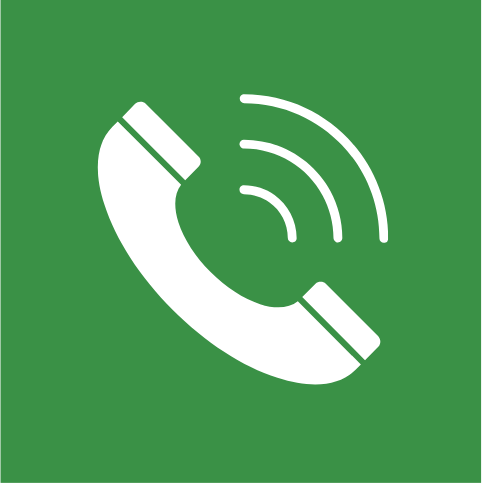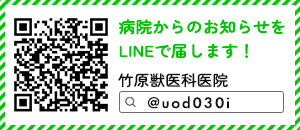犬に“イボ”を発見したら…治療すべき?犬の皮膚にできるイボの原因や種類、主な治療法などについて詳しく解説します2024.06.05

愛犬とスキンシップをしたとき、皮膚にイボのようなものを見つけると不安ですよね。
被毛に埋もれているので、小さいイボなら気づきにくいかもしれません。犬が「痛がらない」「痒がらない」なら飼い主様の発見が遅れることもあるでしょう。
さまざまな色や形、大きさがある“イボ”。「小さいイボだから様子見でも大丈夫?」「大きいイボで不安…。すぐにでも受診すべき?」など、飼い主様にとってはどうすべきか相当不安になるかもしれません。
そこで、今回は犬のイボにはどんな種類があるか、イボの発生原因や治療法にも触れながらのイボについて詳しく解説してきます。
目次
犬のイボって何?
そもそも「イボ」という医学用語はなく、多くの場合、“皮膚に見られるできもの”を指す言葉として知られています。「イボ」や「しこり」、「できもの」などと言うケースが多いでしょう。
イボの見た目は、
・大きさ⇒数㎜ほどの小さなイボ、数㎝程度の大きいイボなど
・発生部位⇒頭や口唇、目の周り、足、肛門周りなど
・色⇒白やピンク、黒など
・形状⇒ニキビのようなもの、丸いもの、カリフラワーのようなもの
など、さまざまなタイプがあります
どうしてイボが…?犬にイボができる原因について

次に、イボができる原因や背景について見ていきましょう。
免疫が低下している
犬のイボは、免疫が低下したとき、つまり“弱っている身体”に発生しやすいです。
通常、動物の体には体に害を与えるウイルス・細菌などをバリアする「免疫機能」が備わっています。免疫が高ければウイルスや細菌から体を守ることができますが、免疫が低下した体は体調を崩しやすく、イボが出ることもあります。
病気によって体力が落ちている犬は、免疫が低いので「イボ」が発生しやすいといえるでしょう。
シニアの犬もイボができやすい
人間にも同様のことが言えますが、犬も高齢になるほどに免疫が下がり、「イボの出来やすい体」になってしまいます。犬は1年で人の5年分歳をとるとも言われています。老齢性のイボが出来始めると、次々と新しいイボが出来始めることも珍しくありません。
またアレルギー性皮膚炎や薄毛、かゆみなど、皮膚のトラブルや皮膚病は、比較的若いころから起こります。そういったケースでは、イボやできものも続発して発生する場合がありますので、若い犬でも注意が必要です。
犬のイボの代表的な種類と治療方法を詳しく解説
次に、代表的なイボの種類や治療についてまとめていきます。
皮脂腺の詰まりで起こる「皮脂腺腫」
皮脂を分泌する皮脂腺が詰まって“しこり”になる症状を「皮脂腺腫」と言います。
体のあちこちにできるイボで、まぶたや肛門にできることもあります。ドーム状に盛り上がり、カリフラワーのような“粒”があちこちに発生し異変に気づく飼い主様もいます。
皮脂腺腫は、犬の皮膚に出来るイボのなかでも起こりやすいです。比較的、高齢の犬に発症しやすい症状と言われています。
数週間から数か月程度で自然に小さくなっていくことも多く、患部が増大しないときは経過観察をすることもあります。
一方で、何らかの刺激によってイボが出血・化膿しているときは「切除」「レーザー」などの外科的な処置が行われるケースが多いです。
ウイルス感染で起こる「皮膚乳頭腫」
パピローマウイルスに感染すると起こるのが「皮膚乳頭腫」という良性のイボです。見た目はカリフラワーのようで、ピンクや黒色で「モコモコ」とした形状をしています。
他の犬と接触した際に感染することが多いですが、健康的な犬の場合は感染してもイボはできないでしょう。
免疫が不完全のパピーや、免疫が低下したシニアの犬が発生しやすいイボと言われています。良性の腫瘍ですが、少しずつ大きく変化することもあります。短い期間で極端に増大するケースを除き、経過観察をされるイボです。
ただ、犬が気にして“掻く”などにより出血・化膿すると外科的切除も必要になってくるでしょう。また免疫が低下している背景に、大きな基礎疾患が隠れていないかどうかを、調べる必要があるかもしれません。
皮脂に老廃物や皮脂が溜まって起こる「表皮嚢胞」
表皮嚢胞は、皮脂や老廃物の蓄積が溜まることでできるしこりで、いわゆる「粉瘤(ふんりゅう)」と呼ばれるものです。
小さく炎症もなく痛みもともなわないものが多いですが、内容物が増えることで数㎝ほどと大きくなるケースもあります。
基本的には良性腫瘍なのですが、犬が引っ搔いたり、飼主様が触れたときなどに破けて中身が出ることもあります。
特に、二次的な感染や炎症を起こすと、痛みが増したり突然破裂したりすることもあるため、切除すべきであるケースも多いです。
脂肪がかたまり上のできものになる「脂肪腫」
皮下脂肪などからかたまり状の脂肪のできものが出来ることがあり、これを「脂肪腫」といいます。脂肪腫はさまざまなところに発生し、ニキビのような小さいイボのようなものから、成長して30㎝ものサイズに大きくなるものまであります。
脂肪腫は良性の腫瘍で、柔らかな感触と、成長スピードがゆっくりであることが特徴です。転移する心配もありません。形状は、球形から楕円形、扁平などです。
ワンちゃん自身も違和感がなければいいですが、発生場所や大きさによっては「歩きづらそう」と日常的な動作を阻害してしまうこともあるでしょう。経過観察をしたうえで、犬の健康や日常生活に影響がある場合は、脂肪腫を切除することもあります。
しかし、大きくなりすぎると切除自体が困難になるケースもありますので、まずは小さめのうちに診察を受けることをお勧めします。
犬のイボ…放置しても大丈夫?それとも治療をすべき?

愛犬の体にイボができると、大小問わず「動物病院を受診するべきか」が迷いどころですよね。
犬の皮膚にできたイボは「良性」か「悪性」
犬のイボは、「良性」か「悪性」のどちらかで、良性のものが多く見られますが、いずれにしても「腫瘍」であることが多いです。良性のイボは、小さめで明るい色が特徴です。
一方、悪性のイボは大きくて硬いことが多く、形は不整形、色は黒色~暗赤色の暗色系の見た目である傾向があります。ある時期を境に急に大きくなったり、見た目や硬さが変化したりすることもあります。
また良性のものであっても、感染や炎症を起こすと、突然腫れたり出血したりすることがあります。
良性・悪性の判断は獣医師に
「小さいから良性だろう」と飼い主様の自己判断で放置した結果、1か月も過ぎたころにもっと大きくなっているケースもあります。
良性だと思っていたら悪性の可能性もありますし、逆に「悪性だと思ったら受診後に良性と言われて安堵した」というケースもあるでしょう。
獣医学の観点からきちんと診断してもらい、そのうえで「様子を見るか・治療を進めるか」を判断してもらうことが大事です。
治療が必要なイボとは?
イボには自然治癒するものもあれば、どんどん悪化するものまであります。悪性のイボの場合、すぐにでも何らかの処置を行うことが大事です。
ただ、治療の必要性は、「良性か悪性か」だけでは判断できません。良性でも、なるべく早めに治療が必要なこともあります。
治療が必要なイボの特徴をご紹介していきます。
化膿や出血しているイボ
通常、良性のものなら、イボがあっても健康を害することは基本的にありません。ただ、良性とはいえ、発生した箇所によっては「イボの存在」を気にしてしまう犬もいるでしょう。気にして噛んだり、過度に舐めたりすることで出血し、化膿するリスクもあります。
悪性のイボ
イボが悪性だった場合、自己判断で放置しているうちにもっと重度な症状になる可能性が大きいです。「様子を見ていたらどんどん大きくなった」「初めは1か所だったのに複数か所に広がった」などは悪性の可能性もあるため、できるだけ早く動物病院を受診しましょう。
イボの治療って何をするの?
イボはどんな治療をするのでしょうか。治療方法についてご紹介します。
良性なら経過観察で済むことが多い
獣医師の診断で良性と分かれば、経過観察で様子を見ることも多いです。
ただ、あくまでも病理の知識を持つ獣医の判断による“経過観察”であることが大事です。
自己判断で大丈夫だろうと軽視せず、まずは動物病院を受診することをおすすめします。
当院では様々なイボ治療が、即日実施可能です。
イボには良性から悪性まで様々あり、出来る場所や個数もその子それぞれです。
当院でのイボ治療は、そのケースに合った方法で、飼い主様の希望に沿った治療を提案するために、多くの治療法を実施しています。
全身麻酔による外科手術を除き、基本的に即日実施可能です。
・外科手術による切除
全身麻酔下で日帰りで行います。
・局所麻酔での簡易的な切除
全身麻酔を希望されない場合や、全身麻酔がかけられない場合に、局所麻酔で切除を行います。
1時間程度の預かりが必要な場合が多いです。
・窒素ガスによる凍結治療
イボに窒素ガスを噴射して、細胞を凍結させることで、イボの退縮や脱落を起こさせる治療です。
体への侵襲がほとんどない安全な方法です。複数回の実施が一般的となります。
・レーザーによる焼烙治療
小さいイボであれば、局所的にレーザーで焼烙することで、イボを切除します。ごく短時間で済みますが、局所麻酔を使用することもあります。
・イボ取り器や糸での結紮による方法
イボに栄養を供給している血流をとめて、イボが自然に脱落するのを待つ方法です。
専用のイボ取り器で、イボの根元に輪っか状の紐を装着する方法や、縫合糸による結紮(縛る)により行う方法があります。治療による痛みはほとんどありません。
イボが発生した箇所によっては、安全のためにしっかりと麻酔をしなければならないケースもありますが、麻酔を使わずに短時間で処置できることもあります。
また、経過観察などの治療を行う場合には、「抗生剤を飲む」「塗り薬をつける」といった治療が行われます。
犬にイボができたらどうすべき?
犬のイボは高齢になるとできるものもあり、完全なる予防はできません。ただ、犬にイボができたときに飼主様ができるポイントを覚えておくと安心です。
イボに触れない、潰さない
犬にイボができるととても気になりますが、あまり触れないようにしましょう。小さな傷から菌が入ったり、「触れること」が刺激となって余計に悪化するリスクもあります。
小さいニキビのようなイボを見ると「潰す」ことで消滅させようと考える飼主様もいるかもしれません。しかし、傷から感染するリスクが高まります。さらに、万が一悪性腫瘍だったときに正しい治療が行えず、愛犬の命を脅かすリスクもあるのです。
また、痛みがあるイボの場合、飼主様が触ったことでもっと痛む可能性もあるため注意しましょう。特に、ブラッシングなどのケアの際に引っ掛からないように気をつけましょう。
愛犬が“イボ”に対してどんな様子かチェック
犬がイボに気づいているかどうかもチェックしましょう。良性で小さいイボの場合、犬は痒みや痛みを感じていない可能性もあります。
逆に、痛痒いイボなら、犬は常に気にしているかもしれません。自分で引っ搔き傷つけることで、状況を悪化させる可能性もあるため気をつけましょう。
獣医師に診断をしてもらうことが大事
良性のイボ・悪性のイボがあり、それぞれ特徴が異なります。
良性のイボは、一般的に“柔らか”で“明るい色味”という見た目で、犬自身が痛がらないのが特徴です。
ただ、飼主様の自己判断で良性だと思ったら、実は悪性だったというケースもあります。良性か、悪性かは獣医師から診断してもらうことが大事です。
まとめ
犬の体に出来たイボは、いつしか自然に消滅するものもあれば、どんどん大きくなってやがて体に悪影響を及ぼすものもあります。悪性のイボはできるだけ早めに発見し、適切な処置を行うことが大事です。
そのために飼い主様ができるのは、
・愛犬の体をふだんからよく観察すること
・イボの大小にかかわらず発見したら動物病院を受診することです。
出来始めは小さいイボも、急に大きくなることもあります。
「あれ?もしかしてイボ…?」と気づいたときは、まずはご受診ください。
実際のイボを拝見させていただき、状況に応じた検査もしたうえで判断させていただきます。
切り取る処置が必要なのだろうかというご不安もあるかと思います。
気になる点は何なりとご相談ください。飼い主様のご不安を取り除けるように、治療の流れや方法についてお話させていただきます。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |