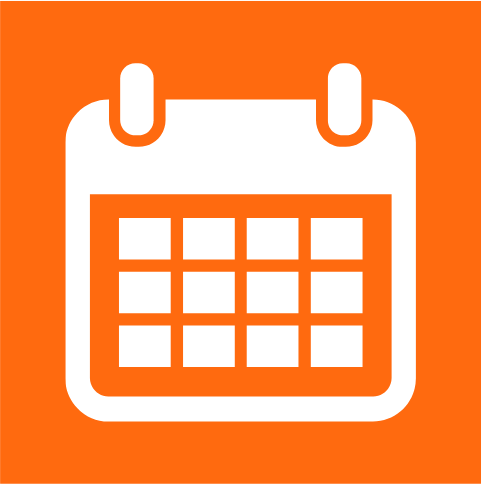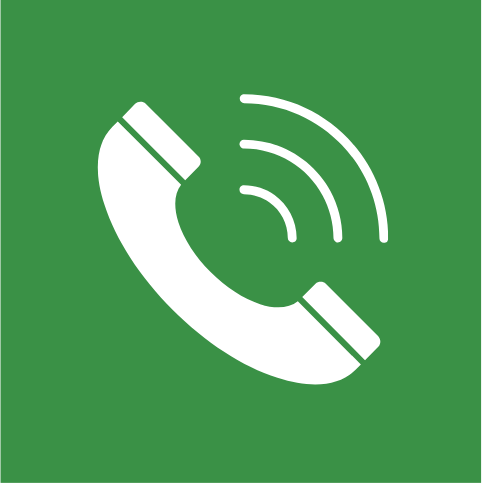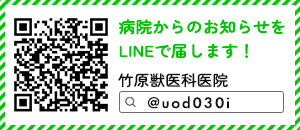犬に歯肉炎の症状が…!?歯茎の腫れや赤みなどの症状やその原因、治療法や対策とは?2024.05.13

犬の歯茎に腫れや赤みがあると不安になりますが、小さい異変の場合、「様子を見ようかな」と放置される方もいらっしゃいます。
でも、それは犬の歯周病のひとつ、“歯肉炎”かもしれません。歯肉炎は歯周病の初期に起こるもので飼主様も気づきづらいことが多いですが、治療をせずにいるとどんどん進行する病気です。犬にとって辛い症状を引き起こす可能性があるので早めに受診をおすすめします。
今回は、歯肉炎の主な症状や犬に発生しやすい原因、治療や予防策について解説していきます。
目次
犬の歯茎が赤い…!歯肉炎の症状とは?
歯肉炎は歯周病の“初期”の段階症状のひとつで、犬自身も傷みや違和感がなく、いつもと変わらずに過ごすことも多いです。飼主様も気づかずにいることもあるでしょう。
そこで、飼主様が犬の口内をできるだけ頻繁にチェックし、早めに気づいてあげることが理想です。
それでは、歯肉炎になった犬に見られる症状をいくつか見ていきましょう。
① 歯石がついてきた
歯磨きケアが不十分な犬の歯には“ペリクル”という膜ができ、それをエサとする細菌や食べカスがついて“歯垢”になります。
歯垢は歯磨きをすれば落とせるほどの柔らかさです。ただ、それを放置すると唾液に反応して石灰化し“歯石”になります。
② 歯茎が赤くなる
本来、健康的な犬の歯茎の色はピンクです。
歯肉炎は歯茎に炎症を起こすため、ピンク色ではなく、赤く腫れます。悪化すると出血し、黒みがかった赤にも見えるでしょう。さらにひどいと膿がでるようになってきます。
③ 口臭がひどくなる
口内が健康的で衛生的なら、口臭がきつくなることはあまりありません。
でも、歯肉炎にともなって腫れや出血をともなうと口臭が発生。今までとは違う口臭が起こるのも、歯肉炎を疑うきっかけのひとつです。
④ 食事がしづらそう
歯茎に炎症が起こっているため、少なからず痛みや違和感があると考えられます。歯肉炎が進行して痛むと、フードを食べるときに気にするようになってきます。
⑤ 前脚で歯を気にする様子
歯肉炎が進んでくると違和感や痛みから、犬も気にするようになってきます。前脚で歯を気にするような仕草も見られるでしょう。
犬は歯肉炎を起こしやすい理由や治療の必要性とは?

もし、犬が歯肉炎を起こしているなら、できるだけ早めに治療をすることが大事です。犬の歯の構造や治療の大切さについてご紹介します。
犬の歯にとって大事な“歯周組織”とは?
まずは、犬の歯の構造について見ていきましょう。犬の歯を支える重要なものが“歯周組織”があります。
歯周組織とは、
・「歯肉」~歯の周りを覆うようにある柔らかな組織
・「歯根膜」~歯槽骨を覆うように存在している膜
・「セメント質」~歯根膜と歯の間にある部分
の4つから構成されています。
歯肉炎は、歯周組織のうち、“歯肉”だけに炎症が起こることを言います。
歯周病は段階的に進行するため、「歯周組織のうちの“歯肉だけ”」に症状が表れるのは初期の頃ということになります。そのうち、周囲の歯根膜やセメント質、歯槽骨にまで広がった炎症が“歯周炎”です。
歯肉炎や歯周炎など、これら歯周組織全体に関わる病気を総合して「歯周病」と言います。
歯肉炎が進行すると起こる症状とは?
はじめこそ歯肉だけの炎症ですが、進行するともっと痛みが広がり、犬にとって辛い症状を引き起こすようになります。
歯肉炎の頃は、歯茎の腫れによる赤みぐらいにとどまります。しかし、歯周炎になってくると「顔の腫れ」「顔に穴があく」「歯のぐらつき・折れ」「鼻水やくしゃみ」「内臓の病気」など全身に深刻な状態をともなうようになるでしょう。特に鼻水やくしゃみの症状がある犬は、歯槽骨が溶けることで、歯の根元に大きな穴が開いて、鼻とつながってしまう「口腔鼻腔瘻」になっている可能性があります。また免疫の弱った犬では、口腔内の細菌が拡がり、肺炎や心臓病のなど全身性の重篤な感染症を引き起こすことがあります。
3歳を過ぎると多くの犬が歯肉炎に
3歳以上の約8割の犬が歯肉炎を患っていると言われています。
ひとくちに「3歳以上の犬」と言っても顔の形や食事スタイルなどが異なるため一概に言えませんが、小型犬や顔が小さな犬は歯垢が溜まりやすいことから歯肉炎を発症しやすい傾向にあるようです。
進行を防ぐには初期段階で治療をすることが大事
お伝えしたように、歯肉炎は「歯周病の初期」に起こる症状です。放置するとひどくなり、犬にとっても飼主様にとっても辛いものです。
初期のタイミングで治療に取り組むことで、症状が悪化するのをおさえられるでしょう。
犬の歯垢や歯石が溜まりやすい理由について
歯肉炎の原因となる“歯垢”。犬は歯垢が溜まりやすい動物です。その理由として考えられる主なものを見ていきましょう。
理由①:細菌の数が多く、アルカリ性
まず、犬の口内は「細菌が多い・アルカリ性」という特徴があり、これも歯垢が溜まる原因のひとつと考えられます。
「犬は虫歯になりづらい」と聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。実は、犬の口内は虫歯菌が繁殖しづらいアルカリ性です。しかし、虫歯にはなりづらい一方で、歯垢や歯石が育つ環境で“歯周病になりやすい”のです。
また、犬の口には多くの細菌が潜んでいます。歯垢は細菌と結びついて“歯石”となりますが、ただでさえ細菌の多い環境ですから、歯垢が歯石化しないようなケアがとても大切です。
理由②:“噛む力”を必要としないフードが普及している

飼い犬の場合、歯垢がつきやすい食事のことが多いです。
自然界にいる野生の犬の食事スタイルは、食べながら「引きちぎる・噛む」というもの。食べ物を噛んでいる過程で歯にこすれ、日々の食事のなかで歯磨きと同じような効果を得ています。
飼われている犬の場合、ほとんど噛まずに飲み込めるような食事も多く、歯垢がつきやすい食事スタイルです。特にウェットフードなどは歯に食べカスがかなり残る食べ物です。
理由③:犬の口は小さく歯が密着、歯垢が溜まりやすい
人間よりも顔が小さい犬は、もちろん“歯”も小さめです。ひとつひとつの歯が密着し合うように歯が連なっているため、歯垢は溜まりやすいでしょう。
飼主様が歯磨きをしても、お口の奥までは届きづらく、細かな隙間がケア不足になっています。もともと歯並びが悪い犬なら、なおさら歯垢が溜まりやすい環境です。
また、“犬の口は細菌が多い”という環境と相まって、一層、歯垢が歯石へと変わりやすいのです。
歯肉炎の治療方法とは?
まずは、動物病院にて歯科検診を受けるのが先決です。
歯周病は「歯肉炎」から「歯周炎」を総称したもので、歯肉炎だけでおさまっている場合なら、歯垢や歯石の除去などが選択されます。
スケーラーと言われる機械でひとつひとつの歯を丁寧に歯石除去行いますが、基本的には全身麻酔による処置です。眠っている間に処置ができるので、犬の安全を確保することができます。硬い歯石や黄ばみのあった歯もとても綺麗になりますし、無麻酔の処置では出来ない歯周ポケットの歯石もしっかりときれいにできるのです。もちろん、口臭もなくなって、お口のなかはとても良い環境になるでしょう。
全身麻酔での処置についてご心配な飼主様もいらっしゃるかもしれません。ときどき、無麻酔で歯垢・歯石の処置ができるという動物病院やペットサロンなどがあります。
しかし、無麻酔での歯石除去では、超音波スケーラーなどの機械を使用できないため、鉗子や半とスケーラーという菌属性の器具が使用されます。その際に歯が折れたり、歯肉から出血したりする危険があります。また犬に与える恐怖やストレスが大きく、処置後に歯磨きをさせてくれなくなることも考えられます。犬にとって安全な方法とは言えず、リスクが大きいので慎重なご判断をすべきです。
また、飼主様のなかには歯肉炎の治療において「歯を抜くのだろうか…?」と愛犬の抜歯を心配される方もいらっしゃいます。
歯茎の炎症だけにとどまっているなら、抜歯までは必要ないケースが多いです。
当院では歯科専用のレントゲンを用いて、1本ずつ歯根を確認し、抜歯の必要がない歯についてはなるべく温存出来るようにしています。一方、見た目上は正常であっても、レントゲンで歯槽骨の融解が著しい歯については、飼い主様と相談の上、抜歯を推奨する場合もあります。
歯肉炎かも…?!飼主だからこそできることとは
愛犬の歯肉炎リスクを減らすために飼主様ができること、そして注意すべきことがあります。
日々のデンタルケアが最も重要

お伝えしたように、犬のお口の中は歯垢が溜まりやすい環境のため、歯肉炎を引き起こすことは多々あります。歯垢が溜まらないように、飼主様が“歯磨き”を日常的にやってあげることが大きな予防策になるでしょう。
ただ、必要以上に力を入れると嫌がられてしまううえ、今後歯磨きできなくなるので注意が必要です。
また、柔らかいウェットフードばかり与えると、犬の小さな歯の隙間にどんどん入りこみ歯肉炎の進行にもつながります。
噛む力を養うことと、歯垢をつきにくくするには、ドライフードがおすすめです。
自分での歯石取りはリスクがある
犬の歯石を取るアイテムが市販されています。
ペット用の“スケーラー”は先端が細く、歯の隙間に溜まった歯石や、歯石を削れるアイテムです。
使い方の写真などを見ると、抵抗なくやらせてくれている犬の様子が見て取れるものの実際は危険がともないます。犬は何をされているかがよく分かっておらず、はじめこそおとなしくしていても、いきなり嫌がって動くこともあるでしょう。
その瞬間に、犬の口や顔、飼主様の手などを傷つけてしまう可能性があります。
市販の歯石取りキットは、ケガのリスクを考えるとおすすめできません。
動物病院で定期チェックと診察を
「ちょっと赤い?」など微々たる変化でもいいので、気づいたことがあれば定期的な歯科健診のつもりでときどき動物病院を受診することをおすすめします。
飼主様が気づきにくかった歯肉炎が見つかるケースもあります。
歯周病は進行すると、犬の痛みも増すほか、治療には抜歯をともないます。“早期発見・早期治療”は犬の負担だけでなく、飼主様のご不安な気持ちも緩和できるでしょう。
他のペットも歯肉炎に~猫が歯肉炎になる原因と対策
犬だけでなく、猫などほかのペットも歯肉炎になります。
口内環境も犬の口内と同じようにアルカリ性ですから、虫歯こそあまりないものの、歯周病になりやすいです。犬と同じように、猫も歯垢が溜まりやすい動物です。
食事をすると歯垢が溜まり、その積み重ねで“歯石”へと変化します。
歯周病の初期なら歯肉炎(歯茎の炎症)で歯石の除去や投薬などで治療できますが、中期~後期段階に突入すると重症化し抜歯の必要性も考えなくてはなりません。歯周病は、老猫はもちろん、若い猫もリスクがあります。
“歯茎の腫れ”は、愛猫のお口が歯周病に侵されかかっているサイン。様子を見ていても自然に治ってはくれない病気ですから、この段階で獣医師から適切な処置とアドバイスをもらうことが大事です。
まとめ:愛犬の歯肉炎対策を徹底して健康長寿をサポート
今回は、犬の歯茎に起こる“歯肉炎”について詳しくお伝えしました。
歯肉炎は歯周病の初期に見られる症状です。犬の口内は歯垢が溜まる環境のため、「歯垢⇒歯石」へとこびり付きやすく、それが歯周病を悪化させる原因となっています。
歯肉炎を予防するには、
・飼主様による丁寧な歯磨き
・ウェットフードを控え、粒の大きなドライフードにする
・動物病院と連携しながらケアをする
歯肉炎を起こさないための飼主様のよるケアが重要です。
日頃から、愛犬のお口のチェックをしておくこともおすすめします。
また、歯肉炎や歯石の蓄積が見られると、歯ブラシだけによる対策では治療ができません。愛犬の長寿のため、動物病院での受診をおすすめします。
「歯茎が赤い気がする」「歯磨きでケアできているか心配…」など、愛犬のお口のご不安やお悩みがあればお気軽にご相談ください。

竹原 秀行
竹原獣医科院 院長
所属:比較眼科学会
| 2019年~ | 川崎市獣医師会 | 顧問 |
| 2011年~2019年 | 川崎市獣医師会 | 会長 |
| 2009年~2011年 | 日本小動物獣医師会 | 理事 |